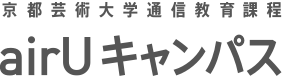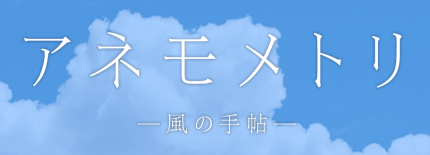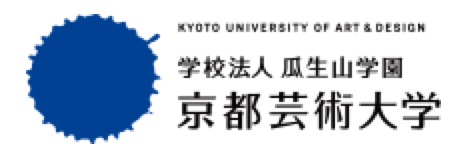佐藤守弘(本学講師)
1839年、写真術が発表されて160年余が経った。本書は、その間に登場したさまざまな技法や思想を多角的に説明するキーワード集である。挙げられた項目は125。それぞれの項目は、有機的にリンクしている。例えば「バウハウス」を調べると、「ニュー・ヴィジョン」や「ストレート写真」という運動と関係していることが判り、「建築写真」というジャンルとの関係、「フォトグラム」という技法との関連も出てくる。
佐藤守弘(本学講師)
最近、久しぶりに大好きなアーロン・エルキンズのスケルトン探偵シリーズを読み返した。主人公は形質人類学者。古い骨を観察し、触るだけで、その人間の性別、年齢はおろか、生きていた時の職業や性向まで当ててしまう。いうまでもなく、これはシャーロック・ホームズ以来の伝統を継いだ探偵像である。探偵小説/推理小説とは、一九世紀後半に生まれた新しい文芸ジャンルである。
佐藤守弘(本学講師)
佐藤守弘(本学講師)
一八七三年、日本政府ははじめて公式に万国博覧会(於ウィーン)に参加した。その時の総責任者であった佐野常民は、報告書に言う。博覧会とは「眼目の教」──すなわち視覚的情報によって人々を教化する装置──であると。まさしくその通りで、博覧会の伝えたメッセージとは、時には国威の発揚であり、帝国主義イデオロギーであり、また時には消費文化の振興でもあった。
佐藤守弘(本学講師)
雪舟等楊の没後五〇〇年を記念して、さまざまなイヴェントや書籍が目白押しである。特に京都の国立博物館での特別展は、異様な人気(数時間待ち!)を呼び、また近く始まる東京国立博物館での特別展もまた大入りになることは今からでも予想できる。しかし、さまざまな取り組みにもかかわらず、そうしたものの多くは、雪舟の「画聖」伝説を追認、再生産に終始しているように感じてならない。
佐藤守弘(本学講師)
本書は、明治天皇の肖像写真を手掛かりに、近代天皇制の為した〈視線の政治学〉を読み解いたものである。〈御真影〉とは、間違いなく戦前の日本で最も有名であった写真(明治天皇の場合、正確に言うと手描きの肖像画を写真で複製したもの)であり、「これほどの政治性を発揮した写真は世界にも類を見ない」のである。そのイメージが、どのように「天皇制国家」を作り上げていったかを語るのがこの書の主眼であるが、「写真論」としても面白い視点を持っている。
佐藤守弘(本学講師)
モノは一体どのようかプロセスを経て、美術品になるのだろう。そこには一体どのような力学が働いているのだろう。昨今では、こうした疑問を共有する者たちが、「美術制度」の批判的研究を繰りひろげている。もはや、「美術品は本質的に美術品たるべき何物かを内包しているからだ」というようなナイーヴな答えで満足する人は少ないであろう。
佐藤守弘(本学講師)
別記の考現学は、一九八〇年代、唐突に復活する。名を〈路上観察学〉と変えて。その中心人物であった赤瀬川原平による〈超芸術トマソン〉──上がって降りるだけの階段、すなわち〈純粋階段〉など、都市のあらゆるところに発見される無用の〈物件〉──は、都市が無意識的に作り上げてしまった〈芸術〉として路上観察の対象となった。
佐藤守弘(本学講師)
イギリスの若者文化には、モッズ、スキンヘッズ、パンクスなど、さまざまな〈トライブ〉が存在した。それらの多くは、特定の音楽を聴き、特定の決まり事を持ち、非常に細かく決められた服装の規則を遵守していた。記号論、ヘゲモニー論などの方法論をもって、本書においてはそれらのスタイルの意味や機能が、精密に分析される。それは、階級やエスニシティと分かち難く関わった記号であった。イギリスにおけるカルチュラル・スタディーズの黎明期に書かれた好著である(翻訳には問題が少々見受けられるが) *記事初出:『季報芸術学』No.15(2001年12月発行)
佐藤守弘(本学講師)
現代日本の視覚文化を考える上で、マンガ(漫画/コミックス)を無視することはできない。マンガについて書かれた書籍/雑誌も多く出版され、「大学生がマンガを読むなんて」と嘆かれたのが遠い昔のことにように思われる。数年前には、美術史学会の全国大会でシンポジウムのテーマに選ばれ、昨年には、日本マンガ学会が発足した。また、いわゆるアートの世界にも、〈マンガ的なもの〉をモティーフとして、あるいは手法として用いる作家が増えている。