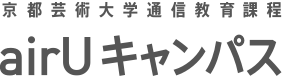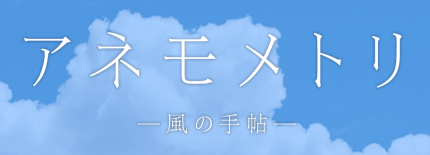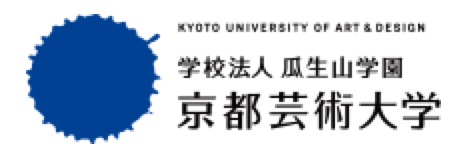金子 典正(教員) 皆さん、こんにちは。金子です。あっという間に6月となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。今月が終われば一年の半分が終わってしまいます。本当に早いですね。さて、今年は年が明けてから新天皇の御即位を記念して全国各地の寺社仏閣で様々な特別公開が行われていますが、先月の今年の奈良国立博物館の正倉院展の発表にあわせて、東京でも正倉院宝物をみることができる「御即位記念特別展 正倉院の世界 皇室がまもり伝えた美」が東京国立博物館で10月14日(月)~11月24日(日)に開催されることが報道されました。奈良国立博物館と東京国立博物館で正倉院宝物を同時に展示するのは初めてのことで、さらに今回の御即位を記念して、いずれも超有名な宝物が久しぶりにお披露目されます。
金子正典(教員) みなさん、こんにちは金子です。いかがお過ごしですか。日頃の研究や勉強は大切ですが、やはり息抜きは必要ですよね。そんな皆さんにお役に立てればよいのですが、今回はわたしが専門とする仏教美術の今秋の主な展覧会情報を整理してお伝えします。スクーリングで瓜生山キャンパス、外苑キャンパスを訪れる際には、時間に余裕があれは是非お出かけください。
金子典正(教員)
会期が残りわずかとなりましたが、上野の東京国立博物館では「特別展 仁和寺と御室派のみほとけ」が3月11日(日)まで開催されています。ツイッター「芸術学コースのつぶやき」でも少し書きましたが、今回の展覧会は仁和寺の至宝はもちろんのこと、全国の御室派の寺院のみほとけが大集合しており、大変見ごたえのある内容となっています。とりわけ大阪葛井寺千手観音像、兵庫神呪寺如意輪観音像、福井中山寺馬頭観音像など、秘仏として大切に伝えられてきた数々のみほとけが信じられないほど間近でじっくり拝見できることは大変有難い機会です。こうした充実した展覧会をみるたびに、大切なご本尊の出開帳をお許しくださったお寺さま、展覧会開催に至るまでの学芸員さんたちの苦労がひしひしと伝わってきて、改めてものすごいスケールの展覧会だと感じました。

熊倉一紗(教員)
みなさんは、ふだん、レポートの準備や授業の予習・復習のため、もしくは小説などを読むため、本を手に取ることは多いと思います。その場合、たいてい「中身」を読むことに集中し、本そのもののデザインに注目することは、あまりないでしょう。しかし、1冊の本には、私たちの感覚を刺激する魅力がたくさん詰まっています。そのことをあらためて思い起こさせてくれたのが、京都dddギャラリーで開催の「平野甲賀と晶文社展」(会期:9月14日〜10月24日)でした。
京都dddギャラリーは、グラフィックデザインを中心に展覧会を企画・展示している数少ない施設(観覧料は無料!)で、大日本印刷株式会社(DNP)が運営しています。この京都dddギャラリーで先日まで開催していたのが「平野甲賀と晶文社展」でした。平野甲賀という名前は知らなくても、カッサンドルのポスターがあしらわれた沢木耕太郎『深夜特急』の装丁家といえばわかる、という方もいらっしゃるかもしれません。
三上美和(教員) 皆さん、こんにちは。ものすごく久し振りの更新ですが、お変わりなくお元気でしょうか。7月に入り、ますます暑くなってきましたね。 先月になりますが、出光美術館「水墨の風 長谷川等伯と雪舟」サントリー美術館「神の宝の玉手箱」(いずれも7月17日まで)に行きました。
同館は、日本で最初の博物館として明治5年に開館以来、美術の愛好者のみならず、研究者、制作者に大きな影響を与えてきた。特別展ももちろん充実しているが、特に常設展は、日本美術史を通史的に鑑賞でき、美術を学ぶ者にとって大変貴重な場所である。一度ならず、展示替えごとに足を運んでほしい。
横浜で活躍した生糸貿易商である原富太郎(号・三溪1868年-1939年)が築いた横浜本牧にある日本庭園。自宅のある内苑とそれ以外の外苑からなる。三溪は多くの貴重な古建築を移築し、明治39年(1906)年、外苑部分を一般に公開。明治末から大正初期、ここで三溪が支援していた今村紫紅、安田靫彦ら若手の芸術家たちを集め、古美術の名品を鑑賞させたことも特筆される。戦後遺族から横浜市に譲られ整備された。
神奈川の歴史と文化を紹介する「総合展示」、所蔵作品展、特別展を開催する。建物は明治37年に建てられた横浜正金銀行で、国の重要文化財に指定されている。毎年開催される芸術学コーススクーリング「現地研修」(横浜、鎌倉)では、三日間の初日、三渓園に続いて訪れている。時折、所蔵作品である古文書や書画が展示、近代以降の横浜の展示にはジオラマも駆使され、立体的に神奈川全域について学ぶことができる。
明治から昭和まで長く活躍した日本画家鏑木清方終焉の地、鎌倉市雪ノ下に建てられた本館では、遺族から譲られた貴重な作品、資料を年数回展示する。こぢんまりとしたスペースを最大限活用した展示がなされている。訪れた際には、同館がここ数年刊行している清方関連の資料集もあわせて読んでほしい。清方研究の拠点としても貴重な場となっている。毎年開催される芸術学コーススクーリング「現地研修」(横浜、鎌倉)では、二日目か三日目に例年訪れている。