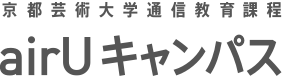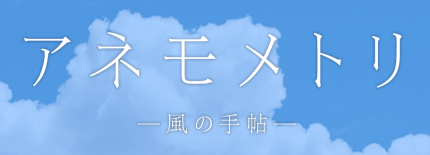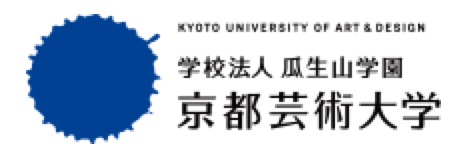梅原賢一郎(芸術学コース教員)
滝田洋二郎監督の『おくりびと』が、米アカデミー賞外国語映画賞を受賞したことは、まだ記憶に新しいことです。葬儀のとくに「納棺の儀」を執行する、納棺師を描いた作品でした(観られたかたもたくさんおられると思います)。 映画に関連して、ある宗教人類学者が、NHKの番組で、次のようなことをいっていました。
水野千依(芸術学コース教員)
芸術と宗教が袂を分かって久しい今日、ふたたびその分水嶺に立ち戻り、像の地位や機能を歴史人類学的に問い直そうとする動きが美術史学において高まっている。本書もまた、造形芸術が自律性を獲得する以前に多くの崇敬を集めた聖遺物に目を向け、「もの」と「像」との複雑な価値付与のメカニズムと崇敬の身ぶりを広範に論じた示唆に富む一冊である。
小林留美(芸術学コース教員)
『シュルレアリスムのアメリカ』というタイトルから、まず、どのような芸術家や作品を、またどのようなトピックスを連想するか、それはこの欄を読まれている皆さんの美術史的知識と関心とによって様々でしょうが、いずれにせよ、簡潔にして魅力的なタイトルには違いありません。そして、「つまるところ、本書はブルトンとグリーンバーグの言説を両軸として構成されるシュルレアリスム美術論であるといっていい」という序の一文が、端的に本書の主旨とその刺激的な論考とを示唆しているでしょう。
中野志保(芸術学コース教員)
従来、美術史研究において、テクストは、視覚的イメージ(以下、「イメージ」とする)を読み解くための手段であり、他方、歴史学や文学史の研究において、イメージは、テクストを補足するものと捉えられてきた。しかし、本書は、イメージとテクストを「分離させて一対一対応で関係性を云々するのではなく、一体化させたうえで、問題群を論ずる方向を拓く、そのための方法論」を模索することを目的に編まれている。